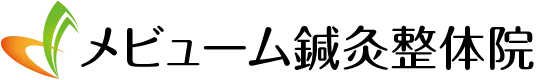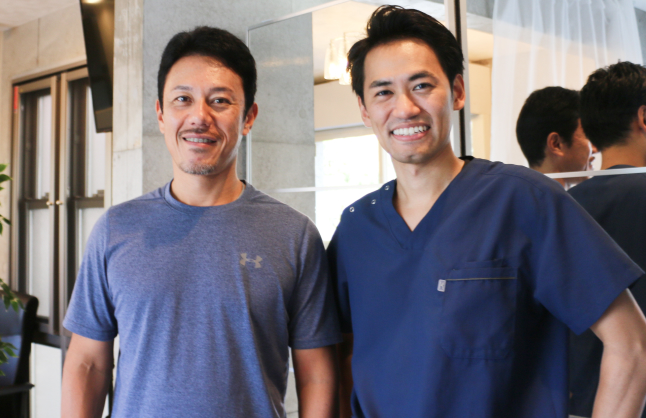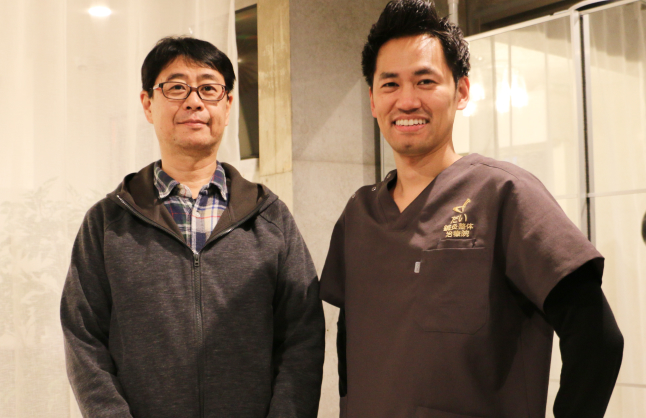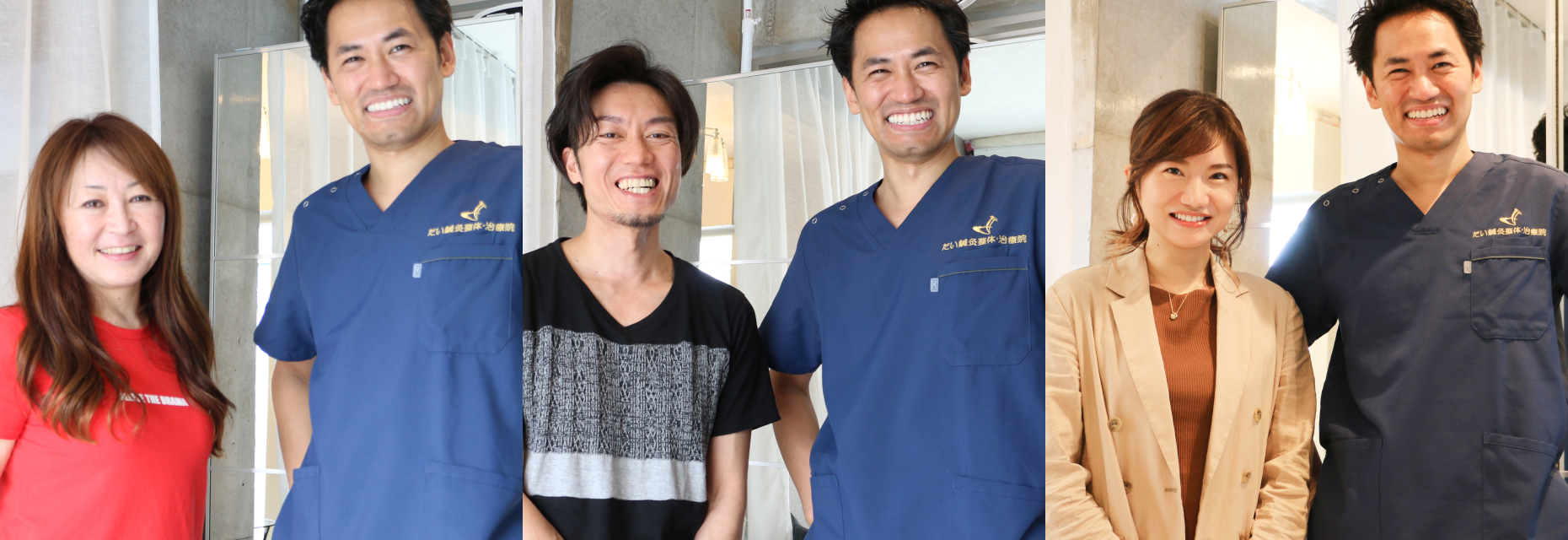起立性調節障害チェック
いくつ当てはまりますか?
基本的な症状
Check
•朝起きるのがつらく、日中もだるさが続く
•立ち上がったときにめまいや立ちくらみを感じる
•頭痛や吐き気が頻繁に起こる
•動悸や息切れを感じることがある
•食欲不振や胃腸の不調を感じることが多い
日常生活での影響
Check
•学校や仕事に遅刻や欠席が増えている
•集中力が続かず、勉強や作業に支障を感じる
•ストレスを感じると症状が悪化することがある
•気温や天気の変化で体調が左右されやすい
•夜更かしや不規則な生活習慣になりがち
結果の判断
〈0~2個〉起立性調節障害の心配は少ない状態です。下記のA・Dの項目を優先して理解しましょう。
〈3~5個〉中程度のリスクがあります。下記のB・C・Dの部分を優先して理解しましょう
〈6個以上〉起立性調節障害のリスクが高く危険な状態です。下記のA・B・C・Dの部分を深く理解しましょう。
A起立性調節障害の初期サインとその重要性
起立性調節障害(OD) は、特に思春期の子どもに多く見られる疾患で、早期発見と適切な対応が重要です。放置すると症状が悪化し、日常生活や学業、健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。以下では、起
立性調節障害の初期サインとその重要性について解説します。
初期段階で見られるサイン
• 朝になると体がだるく、なかなか起き上がれない。
• 学校や仕事への出発時間に間に合わなくなることが多い。
• 急に立ち上がった際にふらつきやめまいを感じる。
• 長時間立っていると気分が悪くなることもある。
• 十分な睡眠を取っても疲れが取れない。
• 日中も集中力が低下し、ぼんやりすることが多い。
• 手足の冷えを感じたり、動悸が激しくなることがある。
• 食欲が減退し、頭痛を伴うこともある。
初期段階を放置するとどうなるか?
起立性調節障害を放置すると、以下のような深刻な影響を引き起こす可能性があります
朝起きられないことで欠席や遅刻が増え、成績や評価に影響する。
症状への理解不足から周囲との関係が悪化し、不安感や自己肯定感の低下につながる。
血流や自律神経の乱れが進行し、慢性的な不調となる。
外出する機会が減り、人間関係や社会活動に支障をきたす。
早期対処の重要性
起立性調節障害は一見軽い症状と思われがちですが、放置すると生活全般に大きな支障を来す可能性があります。初期サインを見逃さず、適切な対応で健康的な日常生活を取り戻しましょう。
B起立性調節障害が改善しない理由
思春期の子どもを中心に多くの人が経験する起立性調節障害(OD)。しかし、適切な対応が行われず、長期化するケースが少なくありません。
なぜなのでしょうか?
それは多くの場合、原因の特定や対策に問題があり、以下のような誤ったアプローチが改善を妨げています。
薬物療法や一時的な生活リズムの調整だけでは、根本的な原因にアプローチできない場合があります。これにより、症状が緩和しても再発しやすい状態が続きます。
起立性調節障害は、自律神経系の不調が大きく関与しています。しかし、自律神経の働きを整えるための包括的なケア(ストレス管理や適切な運動など)が不足している場合があります。
学校生活や家庭環境など、心理的ストレスを引き起こす要因が見逃されることがあります。例えば、過度なプレッシャーや不安定な家庭環境が症状を悪化させることがあります。
起立性調節障害は身体的な症状だけでなく、不安感や自己肯定感の低下といった心理的影響も伴います。これらに対するサポートが不足すると、改善が遅れる可能性があります。
夜型生活や運動不足など、不規則な生活習慣が自律神経を乱し、症状を悪化させることがあります。これらを見直さない限り、根本改善は難しいでしょう。
起立性調節障害を改善するためには、身体・心理・環境の全てに目を向けた包括的なアプローチが必要です。
メビューム鍼灸整体院の施術
~「木も見て森も見る」アプローチ~

メビュームの特徴:木と森の両方にアプローチ
- 木(症状のある箇所): 痛みや不調の原因となる組織に直接アプローチ。
- 森(全身のバランス): 全身の歪みや循環を整え、体全体の機能を高めます。
このアプローチにより、一時的な緩和ではなく、根本的な改善を目指します。
「木」も「森」も丁寧に整え、一時的ではなく根本的な改善へ。効果を実感できる施術で、あなたのお悩みに寄り添います。
一人ひとりに寄り添う
オーダーメイド施術
適切な施術を提供
効果的なアプローチを実現
適切な組織に適切な刺激を施すことで、ソフトな刺激でも強い刺激でも、その方に合った最善の施術を提供します。
初めての方にも安心して受けていただけるよう、丁寧に対応いたします。
メビューム鍼灸整体院の、症状や体質に合わせた施術。

整体、鍼、そしてその両方を組み合わせた施術で、根本的な改善と再発予防を目指します。
メビュームの整体は、痛みや不調の原因となる骨盤や体全体の歪みを整えることに特化した施術です。問題がある筋肉や靭帯(木)の緊張を緩和しながら、骨盤や背骨を含む全身のバランス(森)を重視してアプローチします。
特に、日常生活で支障をきたす痛みや可動域の制限などに対し、姿勢改善を通じて根本的な回復を目指します。
バキバキしないソフトな手技で行うため、ご高齢の方や初めての方でも安心して受けられます。
金額は、全て税込み価格です。 国家資格(柔道整復師・鍼師・灸師・あん摩指圧マッサージ師)を保有する院長がすべての施術を担当いたします。
price
初回12,000円(初見料 : 2,000円 + 施術料 : 10,000円)
2回目以降10,000円
discount
1日 2名様限定
初回12,000円 → 7,000円(税込)
初回はカンセリング検査があるため60分ほどかかります。
メビュームの鍼灸治療では、痛みや不調の原因となる深層筋やツボ(特効穴)に直接アプローチします。これにより血流やリンパの流れを促進し、炎症や筋肉の緊張を効果的に緩和。特に慢性的な痛みや可動域制限がある場合には即効性が期待できます。
また、自律神経を整えることで体内環境を改善し、自然治癒力を引き出します。
進行性の痛みや症状悪化の予防にも対応し、根本的な回復を目指します。
price
初回13,000円(初見料 : 2,000円 + 施術料 : 11,000円)
2回目以降11,000円
discount
1日 2名様限定
初回13,000円 → 8,000円(税込)
初回はカンセリング検査があるため60分ほどかかります。
メビュームが誇る「鍼+整体」の施術は、痛みや不調改善に向けたトータルアプローチです。
鍼灸で深層筋やツボへの刺激を行いながら、整体で骨盤や全身のバランスを調整。根本的な改善だけでなく、動作改善や再発予防まで視野に入れた包括的なケアが特徴です。
症状の進行度や個別の状態に応じたオーダーメイド施術を行い、内側(筋肉・靭帯)と外側(骨格)の両面から同時にアプローチすることで、高い効果が期待できます。
price
初回14,000円(初見料 : 2,000円 + 施術料 : 12,000円)
2回目以降12,000円
discount
1日 2名様限定
初回14,000円 → 9,000円(税込)
初回は問診票記入、カンセリング・検査があるため60~90分ほどかかります。
起立性調節障害についてよくある質問
1. 急に立ち上がること:血圧が急激に変化し、めまいや失神を引き起こす可能性があります。 • 手足が冷える場合:血流を促進するために温めるのが効果的です。特に足湯や腹部を温めることで全身の循環が改善します。 • 軽い運動は血流を改善し、自律神経の安定に役立ちます。特にストレッチやヨガ、水中ウォーキングなど、負担の少ない運動がおすすめです。 • サポーターや弾性ストッキングは、下肢への血液プールを防ぎ、血圧低下を軽減する効果があります。ただし、長時間使用すると逆効果になることもあるため、適切な使用方法を専門家に相談してください。 • 鍼灸治療や整体で自律神経を整えることで症状の緩和が期待できます。また、生活リズムの改善(早寝早起き) や適切な水分・塩分摂取も重要です。 • 動かして良い場合:軽度で体調が安定しているときには、軽いストレッチや深呼吸などで血流を促進するのが効果的です。 1. 内関(ないかん):手首内側中央に位置し、自律神経を整え吐き気やめまいを緩和します。
2. 無理に運動すること:体調が悪いときに無理をすると、症状が悪化する場合があります。
3. 睡眠不足を放置すること:生活リズムの乱れは症状を悪化させる大きな要因です。
• 頭痛や吐き気がある場合:冷たいタオルで首や額を冷やすと症状が緩和することがあります。ただし、長時間冷やしすぎないよう注意してください。
• ただし、体調が悪いときやめまいが強いときは無理せず安静にしましょう。
• 食事では鉄分やビタミンB群を意識して摂取することで、血流改善やエネルギー代謝をサポートします。
• 安静が必要な場合:朝起きた直後や体調不良時には無理せず横になり、体を休めることが大切です。
2. 足三里(あしさんり):膝下4本指分外側にあり、全身の血流改善とエネルギー補充に効果的です。
3. 百会(ひゃくえ):頭頂部中央に位置し、自律神経バランスを整え、頭痛やめまいを軽減します。